赤坂見附・紀伊国坂―のっぺらぼうと西欧化
2013-07-02 10:42:00
「東京の、赤坂への道に紀国坂という坂道がある――これは紀伊の国の坂という意である。何故それが紀伊の国の坂と呼ばれているのか、それは私の知らない事である。」小泉八雲の代表作『怪談』所収の「狢(むじな)」は、こうして始まる。文中にある紀国坂とは、紀伊国坂のこと。八雲が「知らない事」と言っているこの坂の謂れは、江戸時代、現在の赤坂御所、迎賓館のある敷地をはじめ、このあたり一帯に紀伊和歌山藩徳川家上屋敷(上屋敷とは大名とその家族が住む屋敷のことで、江戸城の近くに置かれた)があったことに由来する。最寄りは地下鉄の赤坂見附駅。赤坂見附の交差点から、首都高速4号新宿線と平行して四谷方面に登ってゆく途中の坂道が紀伊国坂である。
 赤坂見附交差点近くでまず目に付くのが弁慶橋。貸しボートもある長閑な佇まいだ。
赤坂見附交差点近くでまず目に付くのが弁慶橋。貸しボートもある長閑な佇まいだ。
『怪談』は、小泉八雲が、妻・セツから聞いた日本各地の伝説や怪異譚を再話したもので、有名な「耳なし芳一のはなし」「雪女」「ろくろ首」、そして冒頭に引いた「狢」など17編からなる『怪談』と、3編のエッセイ『虫界』を合わせて『怪談』として1904年に出版された。「狢」のストーリーは、大変有名なので改めて記すまでもないかとは思うが、念のためあらすじを紹介しておこう。
街灯や人力車が登場する以前、紀伊国坂のあたりは夜になるとたいそう暗く、日没後ともなると、この坂を避けて遠回りをしていた。狢が出るからだ。最後に狢を見た人物は、約30年前に死んだ年老いた商人。ある晩遅くにこの商人が紀伊国坂を急いで登っていると、濠の縁に屈みひどく泣いているひとりの女がいた。身なりもちゃんとしたこの女を見た商人は、身投げでもするのではと思い、足を止め、声を掛けた「お女中、そんなにお泣きなさるな!」。女は着物の袖で顔を隠し泣き続ける。さらに声を掛け続けていると、ようやくその女は商人の方を振り返った。見ると、目も鼻も口もないのっぺらぼう。商人は叫び声を上げて一目散に紀伊国坂を駆け上った。恐怖に怯え、ひたすら走っていくと、蕎麦屋の屋台の提灯が目に入った。蕎麦売りの足元に身を投げ出して、商人は喘ぎながら「私は見たのだ……女を見たのだ――濠の縁で――その女が私に見せたのだ……ああ! 何を見せたって、そりゃ云えない」と言う。「へぇ! その見せたものはこんなものだったか?」と自分の顔を撫でながら言った蕎麦屋の顔は、卵のようになり、同時に提灯の灯りも消えてしまった。
 赤坂見附駅方面から紀伊国坂に入る入り口に立てられている札。謂れも書かれている。
赤坂見附駅方面から紀伊国坂に入る入り口に立てられている札。謂れも書かれている。
狢とはアナグマを指すようで、狸や狐と同様、古来よりひとを化かすもの、つまり妖怪のひとつと考えられていた。弁慶堀のまわりは、今でも樹々に被われ鬱蒼としているのだが、それが街灯のない昔なら尚のこと、その向こう側に潜む「なにか」をひとびとは意識したに違いない。あちら側とこちら側の彼岸にある暗闇としての坂道が現在はどうなっているかを確かめるべく、私は逢魔が時を狙って、この紀伊国坂を訪れてみたのであった。
 まさに暮れようとしている時間帯の紀伊国坂。右手には首都高速が走る。
まさに暮れようとしている時間帯の紀伊国坂。右手には首都高速が走る。
近年のランニングブームからか、走っているひとが多いことにまず気付いた。赤坂見附方面からだと上り坂なので、適度に負荷が掛かってよいのだろう。今や狢が出ずともひとは走るのである。道幅全体は比較的あるのだが、車道がメイン。車道を挟んでお堀側と迎賓館側に歩道がある。いつものようによく調べもせずに歩いているものだから、実は紀伊国坂に辿り着くまでに、この辺りを彷徨うことになったわけだが、何しろ坂の多いエリアである。九郎九坂、牛鳴坂、弾正坂など、様々な坂に出会った。近くには夥しい数の赤い提灯で知られる豊川稲荷東京別院(本院は愛知)があり、凛とした空気を醸し出していた。
 豊川稲荷東京別院の境内。善神・豊川ダ枳尼眞天が白い狐に跨がっていたことから稲荷の名が。
豊川稲荷東京別院の境内。善神・豊川ダ枳尼眞天が白い狐に跨がっていたことから稲荷の名が。
上りは迎賓館側を歩き、紀之国坂の信号(ここが紀伊国坂の終わりだ)も越えて、若葉東の信号まで来た。横断歩道を渡ると新宿区。右手には上智大学があり、そのまま直進すれば四谷駅まで行ける。若葉東でお堀側に渡り、四谷方面に目をやると、随分先まで見晴らしが利く。そこから坂を下って、再び紀之国坂の信号へ。ここで左に曲がると喰違見附跡(江戸時代初期の江戸城外郭門のひとつであり、1874年にはここで岩倉具視暗殺未遂事件「喰違の変」が起きている)を通って紀尾井坂に抜けることが出来る。喰違見附跡はこの辺りでは高い場所にあるのだが、夜、暗くなって下を覗くと転がり落ちそうな急斜面で、狢とはまた違った恐怖を味わえる。再び紀伊国坂に戻り、赤坂見附駅の方まで下りてメトロに乗った。
 赤坂迎賓館東門は、紀伊和歌山藩徳川家上屋敷の一部が明治32年に移築されたものだ。
赤坂迎賓館東門は、紀伊和歌山藩徳川家上屋敷の一部が明治32年に移築されたものだ。
小泉八雲が日本に来たのは1890年(明治23年)。前年に大日本帝国憲法が制定され、近代国家としての基礎が作られつつあった頃である。出雲に古くから残る風俗、風習について考察を巡らせた最初の著作『知られざる日本の面影』(1894年)で、西欧化してゆく日本ではなく、霊的な存在としての古い日本の美しさを説いた八雲にとって、それらが後方に追いやられてゆくのは何とも言えない心持ちだったのではないだろうか。ここで「狢」の中の、「最後に狢を見たのは、約30年前に死んだ年老いた商人」というのを思い出してもらいたい。来日後、妻が語る民話や伝説を再話しているわけだから、大雑把に計算するとその商人が死んだのが1860年頃。死ぬ直前の出来事とも思えないので、商人が狢に化かされたのは、だいたい1850年代と考えてよさそうである。黒船が1853年であり、ここからが幕末と言われる時代だ。おそらく、八雲が想定したのは、これよりも少し前だろう。『怪談』は再話文学だが、八雲の解釈による創作部分もある。つまり、ペリー来航から開国、西欧化に突入してゆく過程を、美しい霊的な日本の死と捉え、それを「年老いた商人」に投影しているのではあるまいか。幕末以前の日本は、狢に化かされるような不思議な出来事が起こる国だった。それが、西洋文化の大波の到来とともに消え失せた。八雲が来日した頃の日本には、もう狢は出ないのである。狢がのっぺらぼうに化ける代わりに、街が、国がのっぺらぼうになってしまった。提灯の灯りが消える代わりに、一晩中街灯やネオンがハレーション気味に街を無表情に溶かしてゆく。
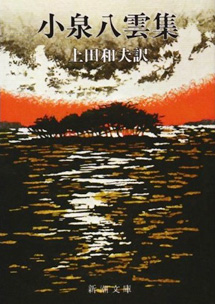
代表作『怪談』のほか、『影』『日本雑記』『心』などからなる、小泉八雲の作品集。
八雲が魅了された「美しい日本」が凝縮されている。/
『小泉八雲集』小泉八雲(著)上田和夫(訳)新潮文庫刊
BEAMS クリエイティブディレクター
BEAMS RECORDS ディレクター
1968年東京生まれ。明治学院大学在学中にアルバイトとしてBEAMSに入社。卒業後社員となり、販売職を経てプレス職に。〈BEAMS RECORDS〉立ち上げや、ウェブ・スーパーバイザー兼務などの後、2010年より個人のソフト力を活かす、社長直轄部署「ビームス創造研究所」所属。執筆、編集、選曲、DJ、イベントや展示の企画運営、大学での講義など、BEAMSの外での活動を行う。著書に『迷宮行き』(天然文庫/BCCKS)がある。
http://www.beams.co.jp
YouTube